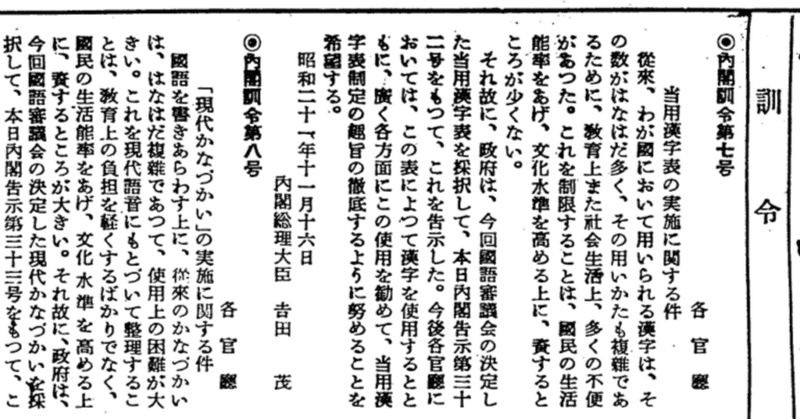即席の言語は腐爛する
プラトンは『国家』の初めの部分を書き上げるのに7回も修正を重ねたそうだ11. アルトゥール・ショーペンハウアー(斎藤忍随訳)「著作と文体」(『パレルガ・ウント・パラリポーメナ』第2巻第23章)、『「読書について」他二篇』(岩波文庫)、岩波書店、1960年、108頁。。この点からもわかるとおり、書き言葉は目に見える形で残り、長き将来にわたって保存されるからこそ、人は文章を書くときには襟を正し、何度も推敲を重ね、よりよいものを書こうとする。ここに、保存性という書き言葉の特徴を見出だすことができる。保存性があるからこそ、記される言葉も一定の規範性を有するようになる。
これに対して、話し言葉は、演説や詩歌の類を別にすれば、即席の言語といっていい。というのも、会話をするにあたっては、瞬時に言葉を発しなければならないし、しかも発した言葉はその場で雲散霧消してしまい、後には残らないからである。必然的に語法や文法は崩れやすくなるし、一貫した法則も成り立ちにくくなる。よって、話し言葉の特徴は、生々しい、いや更に言えば「血腥い」のである。
この続きを読むには